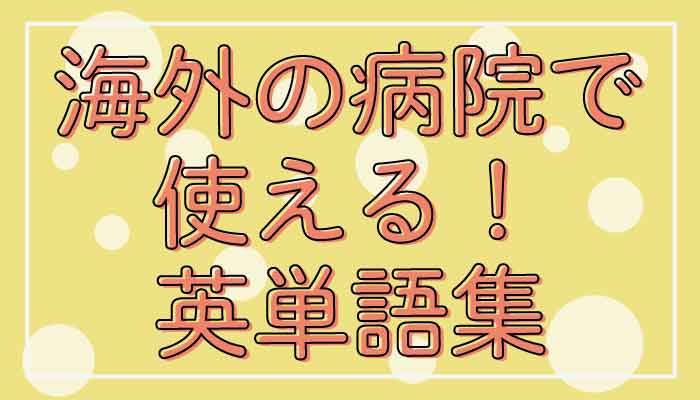ウルグアイ

ウルグアイの安全情報
- 2021-09-07
- 2021-08-14
- 2021-08-12
- 2021-07-28
- 2021-07-17
- 2021-07-14
- 2021-07-07
- 2021-07-06
- 2021-07-03
- 2021-06-26
ウルグアイの気候・風土
ウルグアイ東方共和国は南アメリカ大陸南東部に位置する国で、南米の国々の中でも特に生活水準が高い国として有名です。
国土の多くが草原で、高い山などがないのもウルグアイ東方共和国の特徴の一つです。
気候は温暖湿潤気候に分類され、特に首都のモンテビデオでは過ごしやすい気候が続きます。
国土のほとんどが平地であるため、南極からの寒い風やブラジルを渡ってくる熱風の影響を受けて気温が変化することも少なくありません。
ただし1月にやってくる夏であっても平均気温は23度程度とそれほど暑くはなりません。
ウルグアイ東方共和国内で注意が必要な感染症が寄生虫疾患です。
家畜や犬を通して感染するエキノコックス症、サシガメという昆虫によってもたらされるシャーガス病などがあるので、犬を触ったらしっかりと手を洗い、虫よけはしっかり行いましょう。
南米でよく見られるデング熱はウルグアイ東方共和国内での感染は確認されていません。
むしろサシチョウバエによるリーシュマニア症に注意しましょう。
さらに狂犬病の危険があります。可能であれば渡航前に狂犬病の予防接種を受けておくようにしましょう。
狂犬病は犬から感染するとは限らず、猫やコウモリからも感染の危険があります。特に夕方から夜間に活動するコウモリとは接触しないように注意してください。
渡航前に腸チフスやA型肝炎、B型肝炎、破傷風、狂犬病などの予防接種を受けてから渡航するようにすると、感染症の危険を減らすことができます。
ウルグアイで注意すべき感染症
長期滞在で注意が必要な感染症
- 破傷風
破傷風の菌は日本を含む世界中の土壌の至るところに存在し、怪我をすると傷口から侵入し感染します。感染すると潜伏期間の後に口が開きにくい、首筋が張る、体が痛いなどの症状が出たのち、体のしびれや痛みが体中に...
- A型肝炎
A型肝炎は食べ物や飲み物から経口感染する感染症。日本よりも衛生状況の悪い国で多く見られます。感染すると発熱、全身のだるさ、食欲不振、吐き気、嘔吐などの症状の後、黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなること...
- B型肝炎
B型肝炎は性行為や適切に消毒されていない医療機器の使用などで血液や体液を介して感染する感染症。発展途上国を中心に世界中で広く流行しておりアジア、アフリカ、南米などが高度流行地域です。 感染した場...
- 狂犬病
狂犬病は世界中の多くの国や地域で発生する感染症で、症状が発症した後はほぼ確実に死に至ります。狂犬病ウイルスに感染した犬や猫、キツネ、アライグマ、コウモリなどの動物に噛まれた際、傷口からウィルスが侵入し...
- 腸チフス
腸チフスは多くの発展途上国、特に南アジアで多く見られる感染症です。チフス菌に感染した人の便や尿で汚染された水、氷、食べ物を国にすることで感染が広がります。感染すると1~3週間程度の潜伏期間の後、高熱、...
- 麻しん(はしか)
麻しん(はしか)は日本を含む世界中に存在する感染症です。麻しんウィルスは非常に感染力が強く、空気感染や咳、くしゃみなどによる飛沫感染、接触感染をします。マスクや手洗いだけでは予防することはできないと言...
- 風しん
風しんは日本を含む世界中に存在する感染症です。風しんウィルスは非常に感染力が強く、咳、くしゃみなど飛沫感染で人から人へ感染が広がります。感染すると2~3週間の後に発熱、発しん、リンパ節の腫れなどの症状...
ウルグアイで日本語・英語対応可能な医療機関
| 施設名 | Hospital Britanico(英国病院) |
|---|---|
| 地域 | モンテビデオ |
| 住所 | Morales 2578,Planta Baja |
| 電話番号 | 2487-1020 |
| URL | Webサイトへ移動 |
| 日本語対応 | 不明 |
| 英語対応 | 可 |
| 概要 | 私立総合病院で病床145床 200人の医師,300-400人の看護師(登録看護師は50%)が勤務しています。病床はすべて個室で,CT,MRI,内視鏡検査室も完備されています。医師の多くは英語を話しますが,患者と直接関わるナース,検査技師のほとんどは英語を理解しません。 救急室には小児科,外科,整形外科(外傷科)のレジデントが交代で24時間常駐しており,トリアージが看護師により行われ,専門医が必要な時は専門当番医が呼び出されます。放射線科には腹部エコー装置,MRI2台(1993年にウルグアイで初めて導入),CTが2台あり核医学検査関係は隣接するイタリア病院に依頼しています。 受診に際しては,あらかじめ診療費支払い能力を示す旅行者保険加入証明書やクレジットカードを提示する必要があります。 |
情報源:外務省 世界の医療事情より一部抜粋して掲載